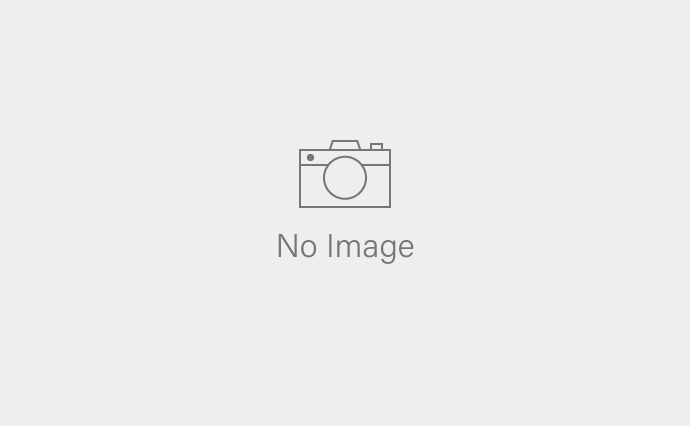日常の中で、子どもに「何度言っても伝わらない」「どうしてできないの?」と感じることはありませんか?
それは、もしかすると「子どもができない」のではなく「大人の声がけが子どもに合っていない」可能性があります。今回は、幼児期の子どもに適した声がけについて考えてみましょう。
子どもにとって難しい大人の声がけとは?
ことばの発達は個人差が大きいですが、一般的に3歳頃から語彙が爆発的に増え、会話が成り立つようになります。しかし、言葉の理解力や記憶力、集中力はまだ発展途上のため、大人が意識して声がけをしないと、子どもには「伝わらない」ことが多くなります。
たとえば、こんな声がけをしていませんか?
1. 指示が長すぎる、やることを一度にたくさん伝える
例:「おもちゃを片付けてから、お着替えして、トイレに行ってね!」
→ 大人には簡単な指示でも、幼児には覚えきれません。一つずつ伝えることが大切です。
【工夫】 「おもちゃを片付けようね」(片付けが終わったら) 「じゃあ、お着替えしようか」 と段階的に伝えましょう。
2. 話すスピードが速すぎる
大人の普通のスピードが、子どもにとっては速すぎることがあります。
【工夫】 子どもに話すときは、意識してゆっくり、はっきり話しましょう。
3. 言葉だけで説明する
子どもの中には、言葉だけでは理解しにくい子もいます。
【工夫】 ・ジェスチャーをつける ・実際にやってみせる ・絵や写真を見せる
たとえば、折り紙をするなら「折る前に完成形を見せる」ことで、ゴールがイメージしやすくなります。
4. 幼児語を使い続ける
「しゅき(好き)」「ブーブー(車)」などの幼児語を、大人が5~6歳の子どもに対して使ってしまうと、正しい発音を覚えるのが遅れることもあります。
【工夫】 子どもの発音がまだ未熟でも、大人はできるだけ正しい言葉で話しましょう。
子どもに伝わる声がけのコツ
では、どのように声をかけたら子どもに伝わるのでしょうか?
1. 短く、わかりやすく伝える
子どもが3語文(「ママ、これ、ちょうだい」など)を話しているなら、大人も3語文くらいで話すと理解しやすくなります。
例:「おもちゃ、なおそうね」「手、洗おうね」
2. 一つずつ指示を出す
「次に何をするのか」を一つずつ伝え、できたら次のことを伝えましょう。
例:「靴をぬごうね」(できたら)「じゃあ、靴をそろえてね」
3. 視覚的なサポートを活用する
・動作を一緒にやってみる ・イラストや写真を使う ・実物を見せる
4. ポジティブな言葉を使う
子どもは否定的な言葉より、肯定的な言葉のほうが受け入れやすいです。
✖「こぼさないで!」 〇「そーっと入れようね」
✖「走らないで!」 〇「ゆっくり歩こうね」
5. 「なんでできないの?」ではなく、「どう伝えたらわかるかな?」と考える
伝わらないときは、子どもが悪いのではなく、大人が「伝え方を工夫する」視点を持つことが大切です。
たとえば、 ✔ 言葉を減らす ✔ スピードを落とす ✔ 一緒にやってみる ✔ 繰り返し伝える
このようにアプローチを変えてみましょう。
まとめ
子どもへの声がけは「伝えた」ではなく「伝わったかどうか」が重要です。
☑ 指示は短く、1つずつ
☑ ゆっくり話す
☑ 言葉だけでなくジェスチャーや視覚情報を使う
☑ ポジティブな言葉を選ぶ ☑ 伝わらなかったら伝え方を変える
こうした工夫を取り入れることで、子どもとのコミュニケーションがスムーズになり、イライラも減るかもしれません。
「伝わらないのは、どうやったら伝わるか考えるチャンス」
だと思って、ぜひ、日常の声がけを見直してみてくださいね!