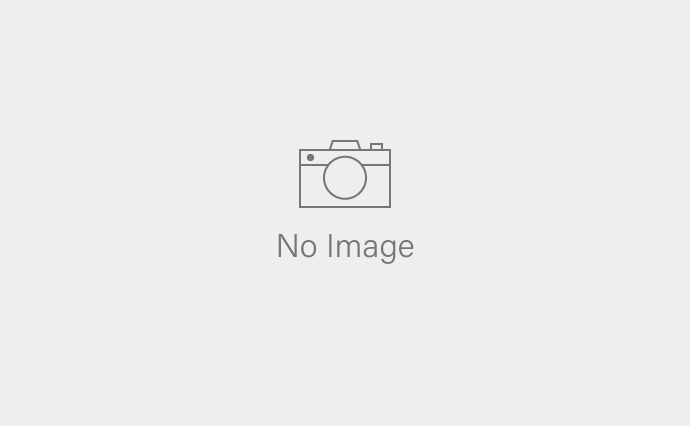子育て相談の現場でよく聞かれる「叱らない子育て」。しかし、多くの方が誤解されているように感じます。
「叱らない子育て」とは、決して「全く叱らない」わけではありません。本来の意味は、「叱ることに依存しない子育て」です。感情的に怒鳴ることなく、冷静にルールを伝え、子どもの成長を支えることが求められます。
幼児期のしつけで叱るべき場面
幼児期において、具体的に叱るべき場面は以下の3つです。
- 危険な行動(例:道路に飛び出す)
- 自分を傷つける行為(例:自傷行為)
- 他人を傷つける行為(例:叩く、蹴る)
どれも、自分や他人に危険を及ぼす行動であり、これらは明確に「ダメなこと」と伝える必要があります。
「叱らない子育て」を誤解し、「子どもの自由を尊重することが最優先」と考えてしまうと、危険な行動を見逃し、結果的に子どもが安全を学ぶ機会を奪ってしまうことになります。特に幼児期は、自分の行動がどのような影響をもたらすのかを理解するのが難しいため、大人がしっかりと教えていくことが必要です。
暴力を容認しないことの大切さ
時々、子どもから叩かれたり、蹴られたりしても
- 「子どもだから仕方ない」
- 「男の子だから少しぐらい乱暴でも良い」
と笑って受け流してしまう方がいます。しかし、これは避けるべき対応です。
暴力を受け流すことで、子どもは誤った学習をしてしまいます。多くのケースでは、お父さんやおじいさんには手を出しませんが、お母さん、おばあちゃん、弟や妹、さらには保育園や幼稚園、学校で「自分より弱い」と思った相手に対して暴力をふるうことを許されると誤解してしまいます。
また、幼少期に暴力を止める習慣がついていないと、小学校に上がったときに他の子どもとのトラブルが増え、友達関係に問題が生じることがあります。周囲の大人が「暴力は認めない」という態度を徹底することで、子どもは人との関わり方を学び、健全な対人関係を築く基礎を身につけることができます。
子どもの暴力を止めることができるのは、およそ8歳頃までと言われています。早い段階で「暴力は許されない」ということをしっかり伝えることが重要です。
暴力を止めるための対応
- 「いやだ」「やめて」と伝える
- 子どもが叩いたり蹴ったりしたときは、感情的に怒鳴るのではなく、落ち着いてはっきりと「いやだ」「やめて」と伝えましょう。
- その場を離れる
- 子どもが暴力をふるう場合、その場を離れることで「相手にされない」ことを理解させます。
- 家族が暴力を受けているのを見つけたら必ず止める
- 誰かが暴力を受けているのを見たら、すぐに止めましょう。
- 暴力から身を守ることを優先する
- 暴力を容認しないだけでなく、「身を守ることが大切」と教えることも重要です。
「叱ることに依存しない」子育てとは?
「叱らない子育て」は「何でも許す」ということではなく、「叱ることに頼らずに子どもを導く」ということです。そのために、日常的な関わりの中で以下のような工夫をすることが効果的です。
- ルールを事前に伝える
- 叱る場面を減らすためには、あらかじめ「これはしてはいけない」と伝えておくことが大切です。
- 例:「道路に飛び出したら危ないから、必ず手をつなごうね。」
- ポジティブな声かけを増やす
- 「ダメ!」と否定するのではなく、「こうしようね」と望ましい行動を伝えることが重要です。
- 例:「おもちゃをそっと、ここに置こうね。」
- 子どもと一緒に考える時間を持つ
- 「なぜこの行動がダメなのか」を子どもと一緒に考えることで、自らルールを理解しやすくなります。
- 親自身が落ち着いて対応する
- 感情的に怒鳴らず、冷静に伝えることで、子どもも落ち着いて話を聞くことができます。
まとめ
✅ 「叱らない子育て」とは、叱ることに頼らず子どもを導くこと
✅ 叱るべき場面は「危険な行動」「自傷行為」「他害行為」
✅ 暴力を受け流すことは、誤った学習につながる
✅ 8歳までに「暴力は認めない」ことをしっかり伝える
✅ 落ち着いて「いやだ」「やめて」と伝え、必要ならその場を離れる
✅ ルールを事前に伝え、ポジティブな声かけを増やすことで、叱る場面を減らす
子育ては日々の積み重ねです。適切な関わり方を意識しながら、子どもが健やかに育つ環境を整えていきましょう。