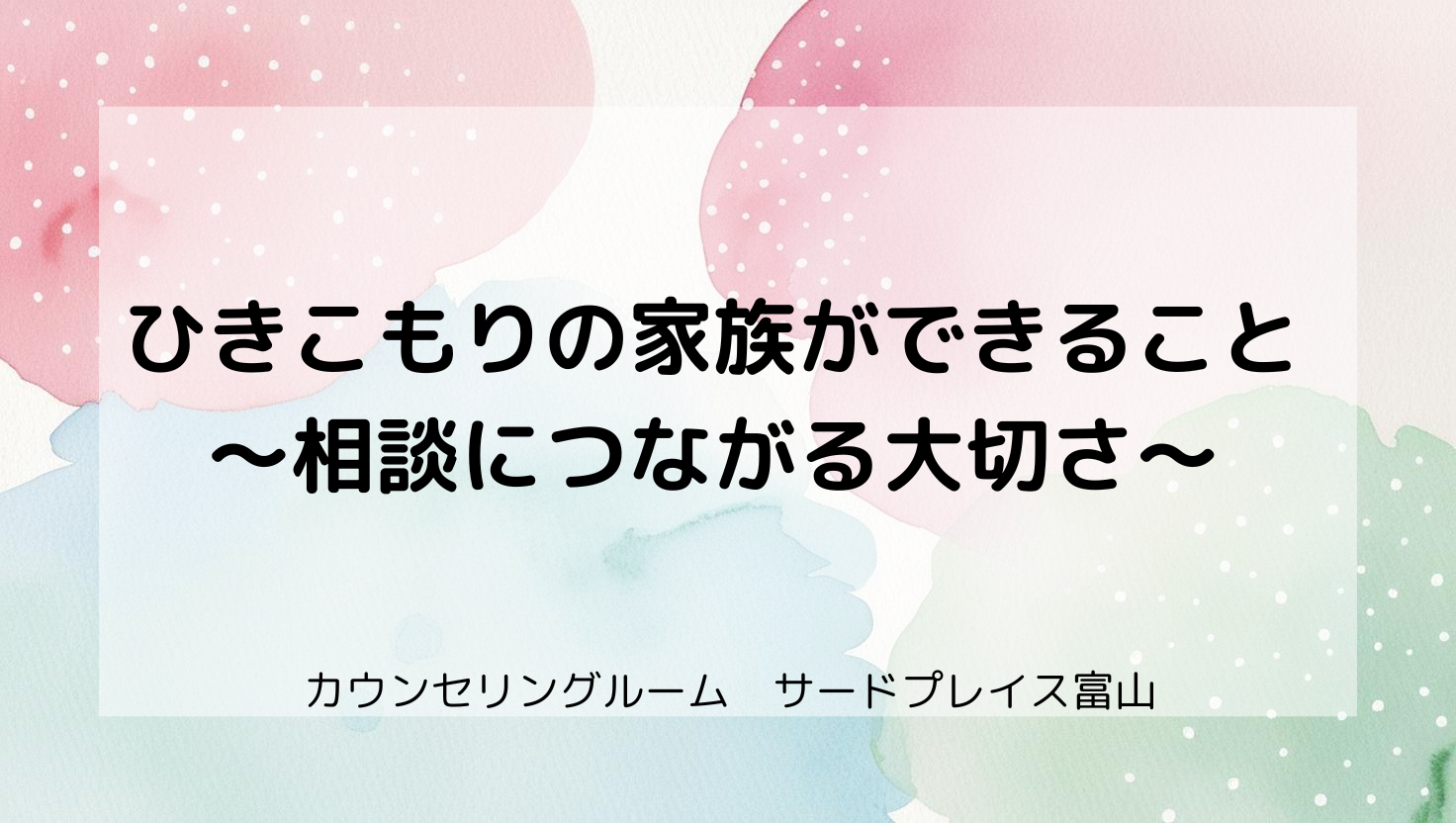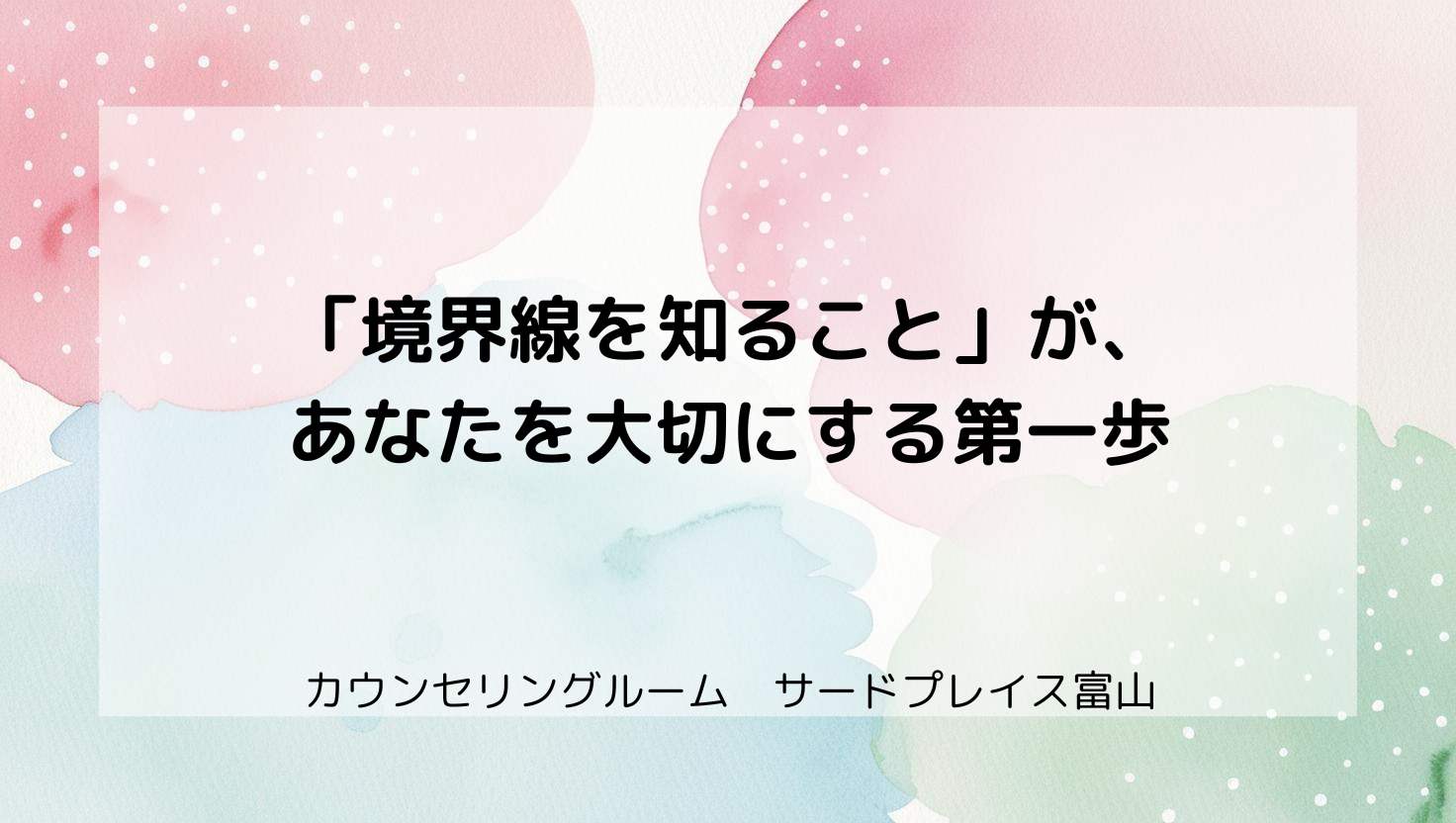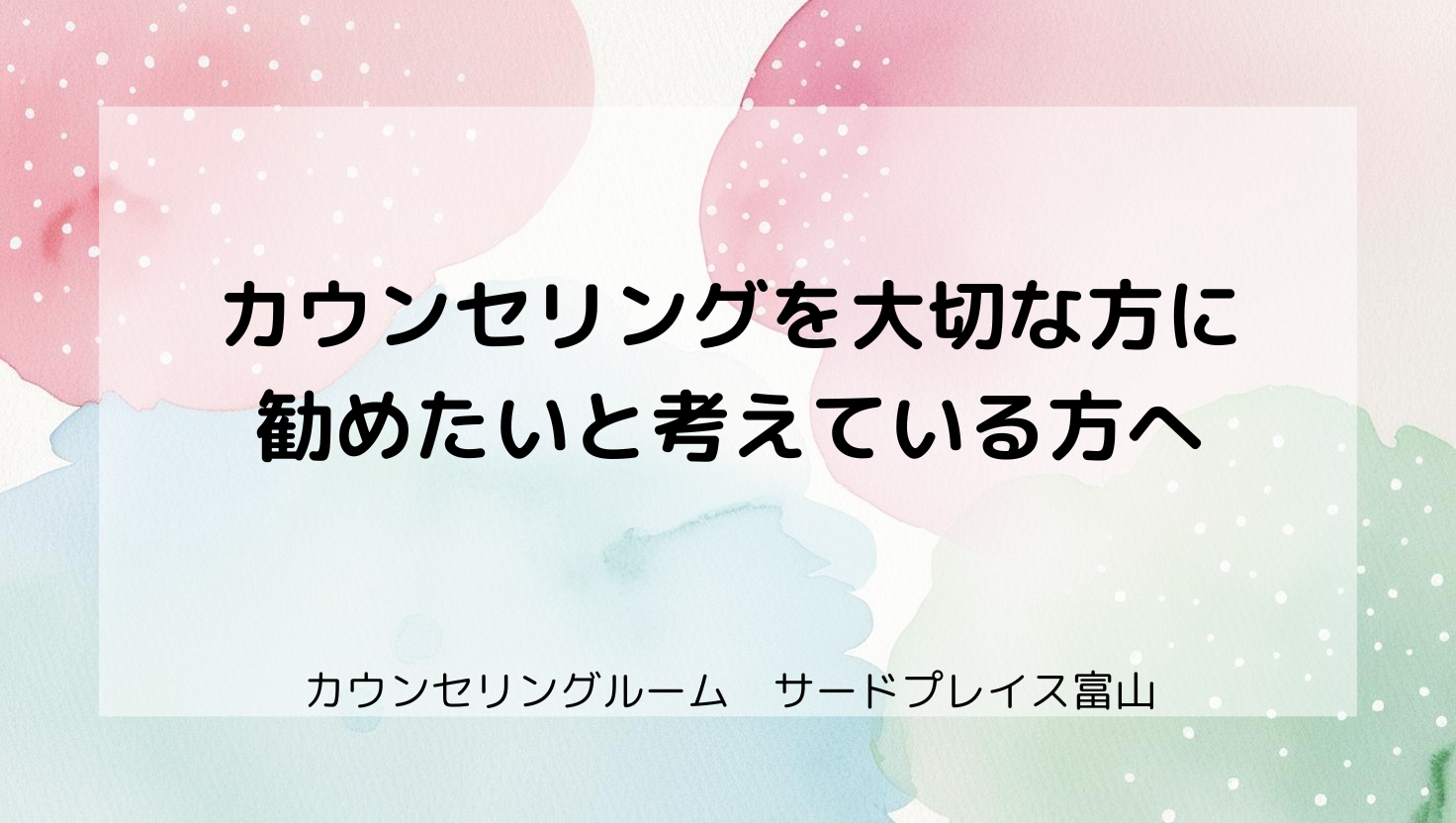お子さんのひきこもりについて、ご家族から相談を受けることがあります。
まず、ひきこもりとは、仕事や学校に行かず、家族以外の人との関わりを避けながら6か月以上家庭に留まり続けている状態を指します。完全に外出しないわけではなく、一人で外出することがある場合も含まれます。
ひきこもりの原因やきっかけはさまざまですが、国の調査によると、半数以上の方が10代からひきこもりを始めているとのことです。親御さんのなかには、「もう少し様子を見ていれば自然と外に出るかもしれない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ひきこもりの状態が6か月以上続くと、さらに長期化しやすくなる傾向があります。そのため、できるだけ早い段階で何かしらのつながりを持つことが大切です。
ひきこもりの背景と影響
ひきこもりの背景には、いじめ、不登校、精神的な不調、人間関係のつまずき、仕事での挫折などさまざまな要因があります。また、社会との関わりが少なくなることで、生活リズムの乱れや精神的な負担が増し、さらに外に出ることが難しくなるという悪循環に陥ることもあります。
特に家族が焦りを感じて無理に外へ促そうとすると、かえって状況が悪化することもあります。そのため、「今すぐ解決しなければ」と焦るのではなく、少しずつ状況を整えていくことが大切です。
ひきこもりの方にとって安心できる場所を見つける
ひきこもりから抜け出すには、「無理をせずに安心して過ごせる場所」とのつながりがとても大切です。例えば、
- 精神科や心療内科の医療機関
- デイケアや自助グループ
- ひきこもり支援を行っている地域の居場所
- 福祉施設や習い事
このような場所では、「頑張らなくてもいい」と感じながら少しずつ外とのつながりを築いていくことができます。
また、家庭の中でできることとして、まずは「安心できる環境を整える」ことが大切です。例えば、
- 無理に会話を増やそうとせず、本人のペースを尊重する
- 家庭内で安心して過ごせる雰囲気を作る
- 少しでも興味を持ちそうな活動を提案する(オンラインの趣味活動など)
本人の気持ちを尊重しながら、少しずつ外との接点を増やしていくことが重要です。
家族が相談につながることが第一歩
お子さんがすぐに相談に行くことが難しい場合、まずは家族が相談機関につながることが大切です。
親御さん自身が相談を続けることで、
- どのように声をかければよいのか
- どんな支援があるのか
- 家族としてどのように関わればよいのか
を学ぶことができ、気持ちにも少し余裕が生まれます。その結果、お子さんに対しても温かく、適切に接することができるようになります。
また、「どう接したらいいのか分からない」「自分たちの対応は正しいのか」と悩んでいるご家族は多いです。決して一人で抱え込まず、専門機関のサポートを受けながら、一緒に考えていくことが大切です。
相談先としての専門機関
現在、国が全国に「ひきこもり地域支援センター」を設置しています。ひきこもりに関する相談を受け付けており、必要に応じて適切な支援機関につなげてくれます。
富山県では、富山市蜷川にある「富山県心の健康センター」内に「富山県ひきこもり地域支援センター」が設置されています。まずは電話相談から始めることができ、相談は無料です。来談を希望する場合は予約制となっていますので、事前に連絡をしてみてくださいね。
また、地域によってはNPO法人や行政が主催する支援団体もあります。各自治体の福祉課や教育相談機関に問い合わせると、適切な支援先を案内してもらえることもあります。
ひきこもり支援には時間がかかる
ひきこもりは、すぐに解決するものではありません。だからこそ、ご家族がまず相談をして、少しずつ支援の輪を広げていくことがとても大切です。
焦る気持ちもあるかもしれませんが、ひきこもっている本人が「安心して過ごせる場所がある」と感じることが、回復の第一歩となります。
ご家族がまず相談につながることで、適切なサポートを受けながら少しずつ前に進むことができます。決して一人で抱え込まず、専門機関とつながりながら、無理のない範囲でできることを一緒に考えていきましょう。
もし相談先に迷った場合は、お住まいの地域の福祉課やひきこもり支援センターに問い合わせてみることをおすすめします。あなたと、あなたの大切な人が少しでも安心して過ごせるように、支援の手を伸ばしてみてくださいね。