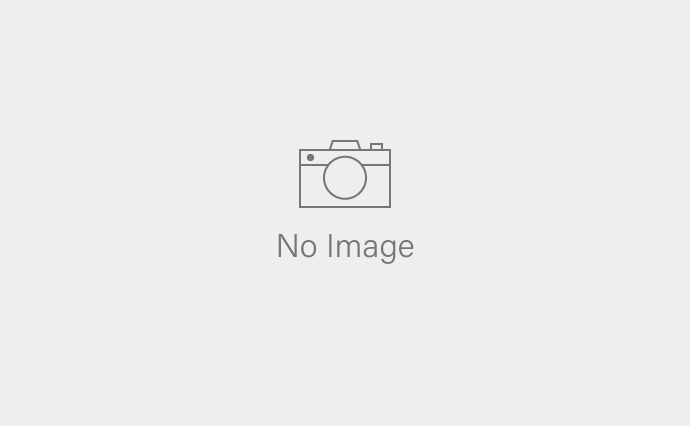「悲嘆(ひたん)」とは、大切な人を亡くしたときに感じる深い悲しみや喪失感のことを指します。これは、ごく自然な心の反応であり、無理に抑え込む必要はありません。亡くなった人を強く恋しく思ったり、喪失の現実を受け入れられなかったりすることは、悲嘆の一部なのです。
悲嘆にはいくつかの段階がある
心理学者のジョン・ボウルビィ(Bowlby)は、人が愛する人を亡くしたときに、次のような4つの段階を経験すると考えました。
- ショックと無感覚の段階(数時間〜数週間)
最初は、現実が信じられず、気持ちが麻痺してしまうことがあります。涙が出なかったり、逆に何も考えられなくなったりすることも。 - 探し求める段階
亡くなった人のことを強く思い出し、「まだどこかにいるのでは?」と感じたり、夢に見たりすることがあります。寂しさが募り、心がかき乱される時期です。 - 混乱と絶望の段階
現実を受け入れざるを得なくなり、強い悲しみや怒り、孤独感を感じることがあります。「なぜ、こんなことが起こったのか?」と考え、時には無気力になってしまうことも。 - 再建の段階
亡くなった人がいない現実の中で、新しい生活を少しずつ築いていく時期です。悲しみが完全になくなるわけではありませんが、少しずつ前を向く力が戻ってきます。
悲嘆は人それぞれ——「課題」を乗り越えていく考え方
ボウルビィのように段階ごとに分ける考え方もありますが、心理学者のウィリアム・ウォーデン(Worden)は、「悲嘆には決まった流れがあるわけではなく、人それぞれ異なるプロセスをたどる」と考えました。彼は、悲嘆を乗り越えていくための4つの課題を提唱しています。
- 喪失の現実を受け入れる
「もう戻ってこない」という現実を少しずつ理解し、向き合うことが第一歩です。 - 悲しみの痛みを感じ、乗り越えていく
無理に明るく振る舞ったり、悲しみを抑え込んだりせず、自分の気持ちを表現しながら時間をかけて受け入れていきます。 - 故人のいない生活に適応する
亡くなった人がいない日常の中で、自分の役割や生活を少しずつ再構築していきます。 - 故人とのつながりを持ちながら、新たな人生を歩む
故人を完全に忘れるのではなく、心の中でつながりを感じながら、前に進むことが大切です。たとえば、思い出を大切にしたり、故人との関係を自分なりに意味づけたりすることで、人生を前向きに歩んでいけるのです。
悲嘆を乗り越えるには
・自分のペースを大切にする(「早く立ち直らなければ」と焦らなくていい)
・感情を抑え込まない(泣きたいときは泣いてOK)
・周りの人に気持ちを話す(信頼できる人に話すだけでも心が軽くなる)
・少しずつ新しい日常を作っていく(無理なくできることから始める)
大切な人を失った悲しみはすぐに消えるものではありませんが、時間とともに少しずつ心は回復していきます。そして、亡くなった人との思い出や愛情は、これからの人生の中で生き続けていくのです。