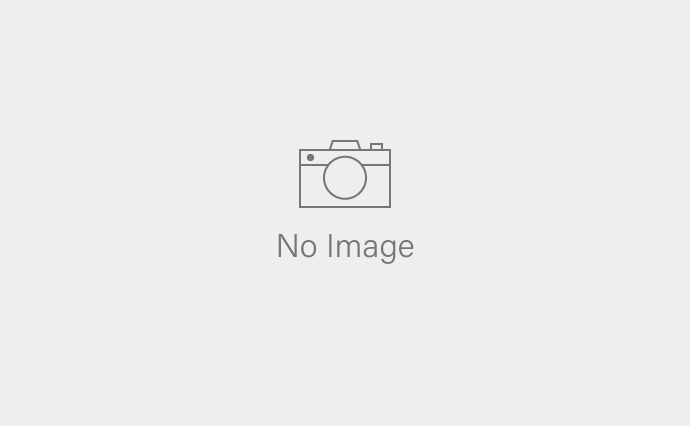「どうしてこれができないんだろう?」「すべきことができないのはなぜ?」 「親の言うことが聞けなくて反抗的なのでは?」 「何度言っても同じことを繰り返して腹が立つ…」
子育てをしていると、こんな疑問や苛立ちを感じる場面が毎日のようにあるかもしれません。でも、実は子どもが「できない」のには理由があります。
できないのは「わざと」ではない
例えば、こんなケースはありませんか?
- 親が「片付けなさい」と言っても、遊びをやめられない
- 「順番を守ってね」と伝えても、待つことが難しい
- 「目を見て話を聞いて」と言われても、落ち着かない
- 「もう何回も言ってるでしょ!」と叱っても、また同じことをする
親としては「ちゃんとできるはず」「何度も教えたのに」と思いがちですが、実は以下のような理由で難しいことも多いのです。
子どもが「できない」理由
1. 脳の発達的に難しい
幼児や児童の脳はまだ発達途中です。大人にとっては当たり前にできる「我慢する」「注意を持続する」「衝動を抑える」といったことが、子どもにとってはとても難しい場合があります。
特に、発達特性のある子どもは、脳の構造上、衝動を抑えたり、落ち着いて行動するのが困難なことも。これは「わがまま」ではなく、「そもそも難しい」ということを理解することが大切です。
2. 言葉の意味を正確に理解できていない
親の指示が曖昧だと、子どもはどうすればいいのかわかりません。
例えば、「片付けてね」と言われても、
- 何を?
- どこに?
- どの程度?
が明確でないと、適切に行動するのは難しいのです。
また、「ちゃんとして」と言われても、「ちゃんと」が何を指すのか、子どもには伝わりにくいものです。
3. 感情が高ぶっていて指示が入らない
怒られたり、不安になったりすると、子どもの脳は「戦う・逃げる・固まる」モードになります。この状態では、親の言葉は耳に入っても、頭には入らず、行動に移すことができません。
「静かにしなさい!」と怒鳴られると、子どもは委縮するか、反発するかのどちらかになりがちです。本来の目的である「静かにする」という行動にはつながりにくいのです。
4. 繰り返し言われすぎて、親の言葉がBGM化している
「早くしなさい!」「片付けなさい!」と何度も言っているうちに、子どもにとって親の言葉は背景音のようになってしまうことがあります。
「また言ってるな」と思うだけで、行動に結びつかなくなるのです。
5. 本人もどうすればいいのかわからない
「静かにしなさい」と言われても、「静かにするってどうすればいいの?」と分からない子もいます。
また、「順番を守ってね」と言われても、具体的にどうすればいいのか、練習が必要な子もいます。
どうすればいい?
「なんでできないの?」と責めるのではなく、
1. 具体的に伝える
「片付けなさい」ではなく、「おもちゃをこの箱に入れてね」と具体的に伝えましょう。
2. 環境を整える
片付けやすい収納を作ったり、待つことが苦手な子には短い時間で区切るなど、環境を整えることも大切です。
3. 短い言葉で伝える
長々と説明するよりも、「おもちゃ、箱に入れてね」「ごはんの時間だから、椅子に座ってね」と短く伝えたほうが理解しやすくなります。
4. 待つ時間を調整する
「順番を守って」と言うだけでなく、待つ時間を短くしたり、楽しく待てる工夫をすると、少しずつできるようになります。
5. 子どもの視線に合わせる
「目を見て話して」と言う前に、肩を軽く叩いて呼びかけたり、子どもの視線の先に行くことで、自然と注目を向けられることもあります。
6. 少しでもできたら褒める
子どもが少しでも対処できたら、「当たり前」と思わずに、「頑張ったね」と声をかけてあげることも大切です。成功体験を積み重ねることで、少しずつ自信を持ち、できることが増えていきます。
まとめ
子どもの「できない」には理由があります。
大人の「ちゃんとやらせなきゃ」という思いが強すぎると、親も子も疲れてしまいます。
「どうしたらできるか?」という視点で接することで、子どもの成長をサポートしながら、親子の関係もぐっと楽になるはずです。
完璧を求めるのではなく、一歩ずつ一緒に成長していく気持ちを大切にしましょう!