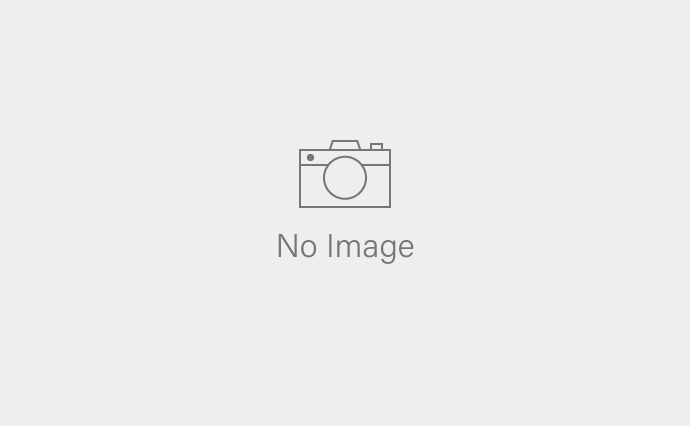毎年4月2日は「世界自閉症啓発デー」です。この日は、自閉症についての理解を深め、偏見や誤解をなくすことを目的とした国連が定めた記念日です。世界中の建物が青くライトアップされるなど、さまざまな啓発活動が行われています。しかし、まだまだ自閉症に関する正しい知識は広まっているとは言えません。そこで、今回は「自閉症とは何か?」をテーマにお話ししたいと思います。
自閉症とは?
自閉症は、発達障害の一つであり、生まれつき脳の働き方に違いがあるために、社会的なコミュニケーションや行動面で特徴が現れます。医学的には「自閉スペクトラム症(ASD)」と呼ばれ、症状の現れ方は人それぞれ異なります。
主な特徴として、以下の4つが挙げられます。
- コミュニケーションの難しさ
- 表情やジェスチャーを使ったやり取りが苦手
- 相手の気持ちを読み取るのが難しい
- 自分の興味のある話題を中心に話しがち
- こだわりの強さ
- 一つのことに強い関心を持ち、繰り返し行う
- 決まった手順やルールを重視し、変更を嫌がる
- 特定の物の並べ方や手触りにこだわる
- 感覚の違い
- 音や光、匂いなどに対して敏感または鈍感
- 服のタグや特定の素材の手触りを嫌がる
- 一定の音や動きを心地よく感じ、繰り返す
- 新しいことに慣れるまでに時間がかかる
- 環境の変化に対して強い不安を感じることがある
- 初めての場所や新しい人と会うときに戸惑いやすい
- 慣れるまでに時間がかかるため、繰り返しの経験が大切
これらの特性は人によって異なり、はっきりと現れる人もいれば、軽度で気づかれにくい人もいます。そのため、「自閉症の人はみんな同じ」というわけではなく、それぞれの個性に合わせた対応が求められます。
自閉症の診断について
自閉症と診断されるのは、1歳半ぐらいで診断される方もいますが、大人になってから仕事や人間関係で自分や周囲の困りごとが多くなって診断されるに至る場合もあります。幼少期には特に目立たなかった特性が、成長するにつれて社会的な環境とのズレとして現れることもあります。そのため、大人になってから診断を受ける人も少なくありません。
自閉症のある人とどのように接すればよいか?
自閉症のある人と関わる際には、相手の特性を理解し、適切な配慮をすることが大切です。
- はっきりとした言葉で伝える
- あいまいな表現や比喩ではなく、具体的な言葉を使う
- 「あとで」ではなく、「○時になったら」など、明確に伝える
- 急な変化を避ける
- 予定が変わる場合は、事前に知らせる
- 環境の変化がストレスになることを理解し、必要に応じて調整する
- 感覚の違いを尊重する
- 大きな音や強い光が苦手な場合は、静かな環境を整える
- 特定の食べ物や触感が苦手な場合、無理に強要しない
- 新しいことに慣れるための時間を確保する
- 初めての場所や出来事に対して、事前に情報を伝えて安心感を持たせる
- 慣れるまでの時間を確保し、無理に急がせない
- 何度か繰り返し経験することで、安心して取り組めるようになる
自閉症のある大人の強み
自閉症のある大人は、自分の得意分野で力を発揮しやすい傾向があります。職場が安心できる環境であり、仕事内容が自分の興味や特性に合っている場合、非常に真面目に仕事に取り組み、高い集中力を発揮することができます。ルーチンワークや専門的な業務において、継続的に成果を上げる力を持つ人も多くいます。
何よりも大切なのは、「普通」に当てはめるのではなく、その人の個性を理解し、尊重することです。
自閉症を理解する社会へ
私たちが自閉症について理解を深めることは、本人や家族にとって大きな支えとなります。誤解や偏見がなくなれば、自閉症のある人たちがより生きやすい社会になるでしょう。
そのために、まずは自閉症について知ることから始めてみませんか? 4月2日の「世界自閉症啓発デー」をきっかけに、周囲の人と自閉症について話してみたり、関連する書籍や映画に触れてみるのもよいでしょう。
当カウンセリングルームにも、自閉症や発達障害に関する書籍がたくさんあります。自分や家族はそうでないかな、と思われた方のご相談も受け付けております。
「理解すること」が、誰にとっても生きやすい社会への第一歩になるのです。