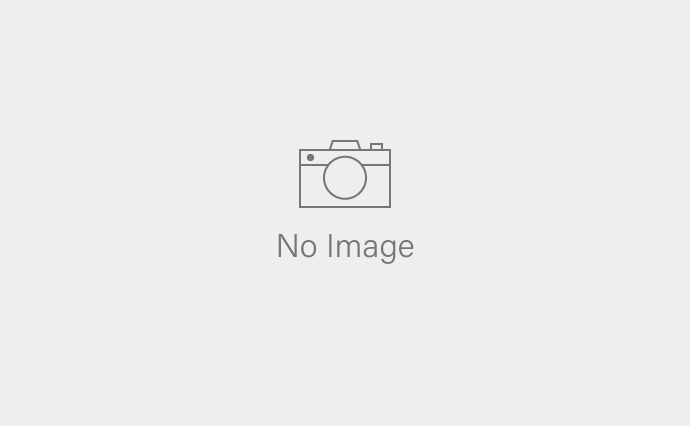私たちは日々、家族や友人、パートナー、職場の人など、多くの人と関わりながら生きています。そんな人間関係の土台になるのが「愛着(アタッチメント)」です。愛着理論は、特に子ども時代の親との関係が、私たちのその後の対人関係にどれほど影響するかを明らかにした理論です。
この記事では、愛着理論とは何か、そして私たちの心や子育てにどのように関わっているのかを、できるだけわかりやすくご紹介します。
愛着ってなに?
「愛着」とは、簡単に言うと「この人とつながっていたい」「そばにいてほしい」と思う気持ちのこと。特に、怖い思いをしたり、不安になったときに「安心させてくれる人」を求めるのは、人間にとってとても自然なことです。
この「安心できる人とのつながり」を求める心のはたらきは、生き延びるための本能的な仕組みでもあります。たとえば、赤ちゃんが泣いてお母さんに抱っこされると安心するのも、愛着行動のひとつです。
愛着はどのように育つの?
愛着理論の創始者であるジョン・ボウルビィは、「赤ちゃんは、生まれてから最初の1年間のあいだに、関わってくれる大人(多くは母親)との経験をもとに、”この人はどう反応してくれるか” を予想するようになる」と述べています。
この「相手がどう反応してくれるか」という予想は、やがて「内的作業モデル」と呼ばれる心の枠組みになります。これは、その後の人間関係のベースにもなっていきます。
つまり、赤ちゃんの頃に安心できる大人とのやりとりをたくさん経験すると、「人って信頼できるんだ」という感覚が心に育ちやすくなります。
子どもの愛着のタイプ
心理学者のメアリー・エインズワースは、赤ちゃんとお母さんの関係を観察するために「新奇場面法(Strange Situation Procedure:SSP)」という方法を考案しました。
この方法によって、1〜2歳くらいの子どもが母親に対してどんな愛着をもっているのかを以下のように分類しました。
- 安定型:母親がいれば安心し、離れると不安になるが、戻ると落ち着く。
- 不安-回避型:母親がいてもあまり関心を示さず、離れても平気そうに見える。
- 不安-両価型:母親にしがみついたかと思えば怒ったり、反応がアンバランス。
- 解体型:恐怖や混乱を示し、一貫性のない行動をとる。
大人にも「愛着のタイプ」がある
さらに研究が進むと、愛着は子ども時代だけでなく、大人になってからの人間関係にも深く関係していることがわかりました。
心理学者のメインらは、大人の愛着を調べるための「成人愛着インタビュー(AAI)」という方法を開発し、次のような分類をしました。
- 安定―自律型:過去の経験をバランスよく振り返り、自分の感情を整理できる。
- 愛着軽視型:子ども時代の経験にあまり触れようとせず、感情を抑えがち。
- とらわれ型:親との関係に強くとらわれ、現在でも怒りや混乱が残っている。
- 未解決型:トラウマや喪失体験が未処理で、語りに一貫性がない。
愛着は「世代間で受け継がれる」
興味深いのは、子どもの愛着のタイプと、その母親の成人としての愛着タイプには深い関係があるという点です。
たとえば…
- 安定―自律型の母親の子どもは、安定型の愛着をもつことが多く、
- 愛着軽視型の母親の子どもは、不安―回避型に、
- とらわれ型の母親の子どもは、不安―両価型になる傾向があります。
- また、未解決型の母親の子どもは、解体型になりやすいこともわかっています。
これらの結果から、愛着のパターンは「親から子へと引き継がれる傾向がある」とされています。これは遺伝というよりも、親子のかかわりの中で自然に伝わっていく、いわば「心のバトン」のようなものです。
最後に
「愛着」は、特別な人だけに関係する理論ではありません。私たちみんなの心の深いところにある、つながりへの欲求を説明してくれる大切な理論です。
そしてもし、「自分は人との関係がうまく築けない」「子育てに自信が持てない」と感じていたとしても、今から少しずつ愛着を育て直すことはできます。
カウンセリングや心理学を活用しながら、自分自身の「愛着のかたち」を見つめ直すことは、人間関係や子育てをよりあたたかいものに変えていく第一歩になります。