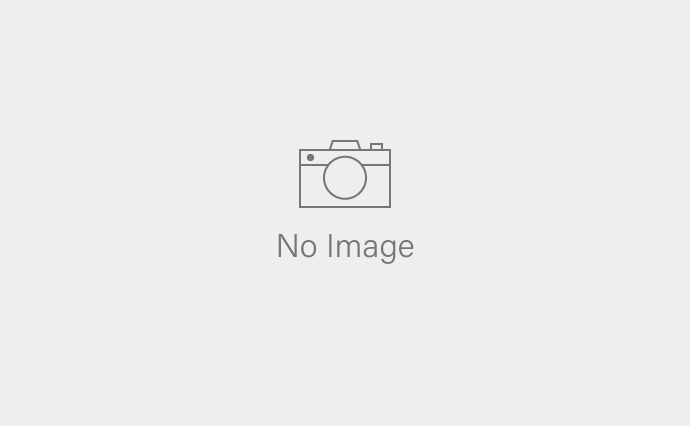「他人の靴を履く(To walk a mile in someone else’s shoes)」というイギリスのことわざを聞いたことはありますか?
直訳すれば「誰かの靴を履いて1マイル歩く」。少し奇妙な表現に思えるかもしれませんが、この言葉は「他人の立場になって物事を考える」こと、すなわち“共感”の大切さを説いています。
現代の社会や家庭、職場では「共感」が求められる場面がたくさんあります。にもかかわらず、私たちはつい、自分の視点だけで物事を判断してしまいがちです。「なんでそんなこと言うの?」「どうしてわかってくれないの?」という気持ちが積もると、人間関係に摩擦が生じやすくなります。
そんなときこそ、「他人の靴を履く」ことが大切になります。
靴には、それぞれの背景がある
私たちは誰しも、自分だけの「靴」を履いて日々を生きています。育ってきた環境、経験、価値観。そういった背景が、その人の「靴」のかたちをつくっているのです。
子どもが朝、なかなか起きてこない。
パートナーが家事を手伝ってくれない。
職場で上司にちょっときつい言葉を言われた。
こうした場面で、相手の言動にモヤモヤを感じることはよくあることです。でも、もしかしたらその相手も、何かしらの「靴」を履いていたのかもしれません。
・子どもは、学校での緊張で心身が疲れているのかも。
・パートナーは、職場でプレッシャーを抱えて余裕がないのかも。
・上司は、過去に失敗してしまった経験があって、今もその傷が癒えていないのかも。
私たちが相手の靴を少しでも履いてみようとしたとき、「どうしてこうなるの?」という疑問が、「そうだったのかもしれないね」という理解に変わっていきます。
共感は、正しさを競うことではない
共感するということは、必ずしも相手の意見や行動に賛成することではありません。
「それは違うと思う」という気持ちがあっても構わないのです。ただ、その人がそのように感じた背景に目を向ける──それが共感の出発点です。
これは、親子関係にも当てはまります。たとえば、子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、「甘えてる」「行かなきゃダメでしょ」と返したくなることもあるかもしれません。でも、「この子は今、どんな靴を履いているんだろう?」と考えてみると、違った対応が見えてくるかもしれません。
「朝、学校に行くのが怖いのかな」
「友達との関係で悩んでいるのかも」
「先生とのやりとりがプレッシャーだったのかな」
こうして子どもの気持ちに少し寄り添えたとき、たとえ解決しなくても、親子の間に「つながり」が生まれます。そのつながりこそが、子どもにとっての安心感になっていきます。
自分自身の靴も、大切に
そして忘れてはならないのが、「自分自身の靴」もまた、かけがえのないものであるということです。誰かの靴を履いてみようとするとき、自分の靴を一度脱がなければならないこともあります。でも、それは自分を否定することではありません。
「私は私なりの事情がある」
「それでも、相手のことを少しでも知りたいと思っている」
そんなふうに、自分自身にも優しくなれたとき、他人の靴を履くことが、少しずつ自然になっていきます。
最後に──靴を履きかえる勇気
共感は、相手との違いを消すことではなく、違いを理解しようとする行為です。そしてそれは、とても勇気のいることでもあります。
すぐにできなくても大丈夫。
ほんの少し、相手の靴を履いてみようとする気持ちがあれば、そこから関係は少しずつ変わっていきます。
今日、もし身近な誰かとの間でモヤモヤを感じたなら、「この人、どんな靴を履いてるんだろう?」と、そっと思い浮かべてみてください。
その問いかけが、あなたと誰かを、少しだけ近づけてくれるかもしれません。